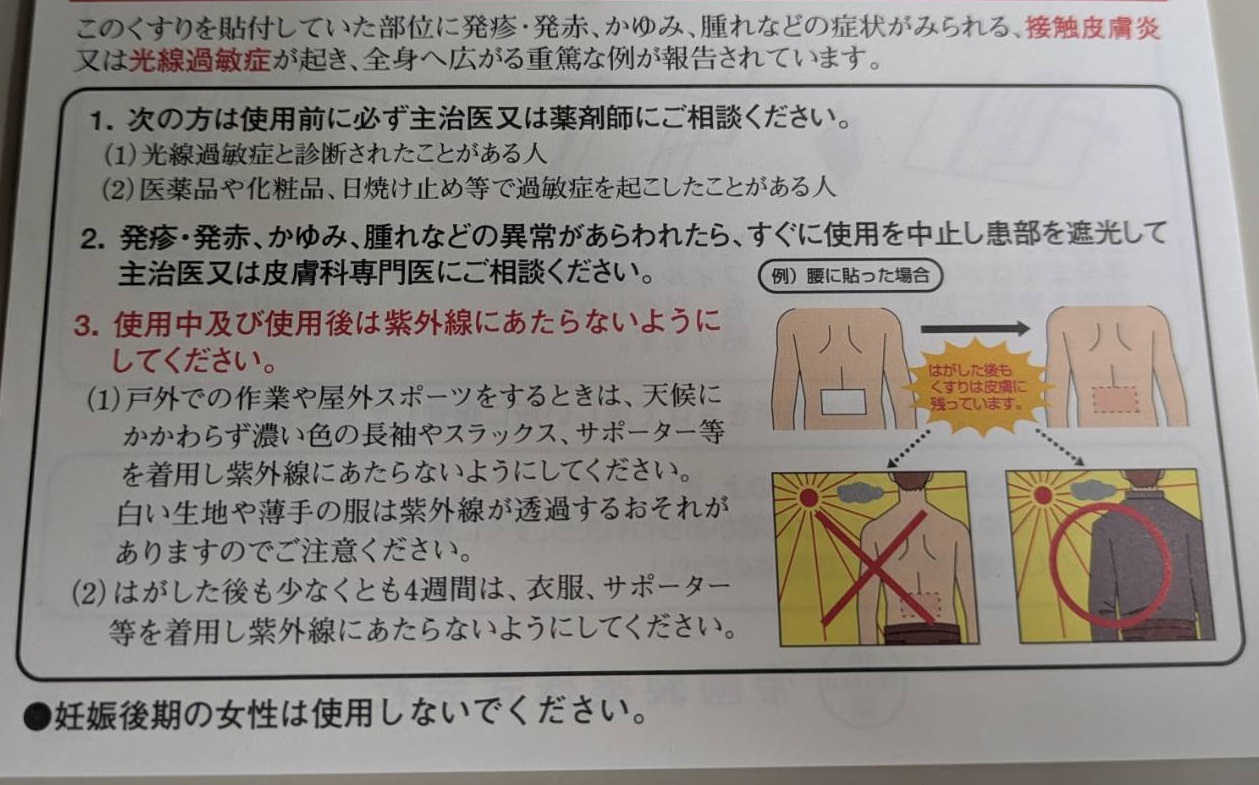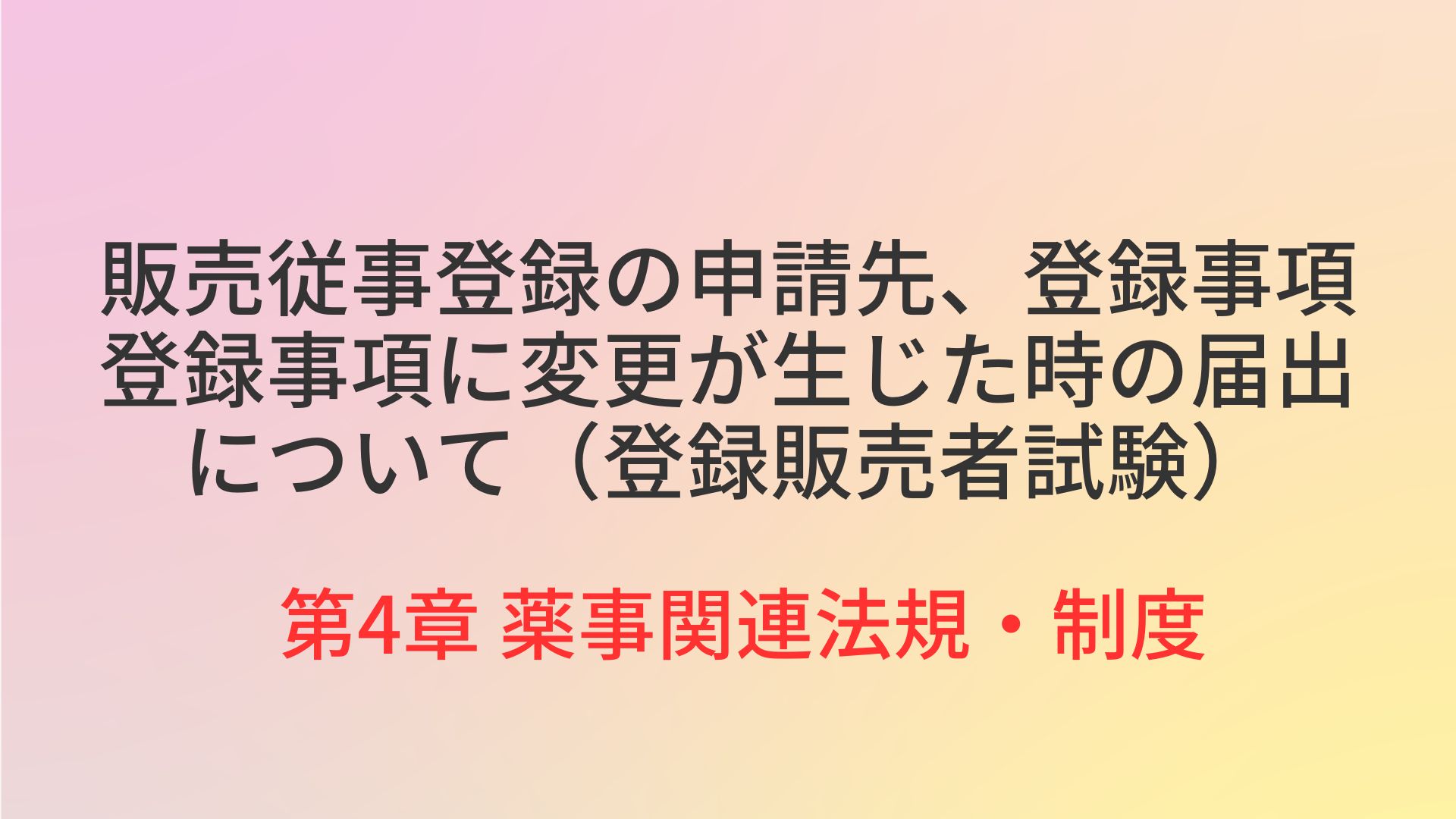医薬品医療機器等法は、簡単にわかりやすく言うと私たちが安心して薬や医療機器などを使えるようにするための法律で、一般用医薬品の販売に関連する法令の中でも、最も重要な法令です。
その正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、通称「薬機法(やっきほう)」と呼ばれることが多いです。(以前は「薬事法」と呼ばれていましたが、2014年の法改正で、近年急速に発展した医療機器や再生医療等製品も管理対象であることを明確化し、名称も変更されました)
その第1条では、この薬機法の目的が記されていますが、簡単に言うと、薬や医療機器などを安心して使えるように厳しく管理・規制すると同時に、新しい画期的な薬や医療機器などが生まれるように研究開発を後押しすることで、私たちの健康を守ることを目指していると述べられています。
他にも、iPS細胞等の研究が進んで、再生医療の実用化に向けた動きに対応するための措置についても盛り込まれているもの特徴です。
なお、この後に「再生医療等製品」という言葉が登場しますが、これは、ヒトの生きた細胞そのものや、遺伝子を組み込んだ細胞などを使い、患者さんの体が本来持っている力を引き出して治療することを目指したものです。
具体例としては、重度の火傷の患者さんの皮膚の一部を採取し、体外で培養したもの(再生医療等製品)を、傷ついた部分に移植して、皮膚の再生を促すような治療に用いられています。
第4章の第一問目で、穴埋め問題として良く出題されている
登録販売者試験・第4章の最初の問題は、この薬機法に関する第一条の穴埋め問題が定番・頻出となっており、これまで頻繁に出題されています。
穴埋めの文章として、第一条に記載されている「薬機法の目的」、「医薬品等関連事業等の責務」、そして「医薬関係者の責務」から出題されますが、特に穴埋め部分になりやすいところや、ポイントを赤字で示しています。
法第1条において、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」ことを定めている。
⇒この条文が最もよく出題されています。
⇒穴埋めのひっかけとしては、「保健衛生」⇒「×公衆衛生」、「指定薬物」⇒「×麻薬・抗精神病薬」、「再生医療等製品」⇒「×生物由来製品」といった感じで、誤り選択枝が登場します。
法第1条の4においては、医薬品等関連事業者等の責務として「医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第4条第1項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(略)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。」
⇒ここはあまり出題されていません。
法第1条の5第1項においては、医薬関係者の責務として「医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(略)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。」旨が定められている。
⇒「獣医師」が穴埋めで出題されたことがあります。「その他医薬関係者」には登録販売者も含まれています。
⇒ここで書かれている通り、登録販売者も、正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報の入手や、自らの研鑽に努める必要があるため、薬機法により薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働省大臣に届出を行った者(研修実施機関)が行う研修を毎年度受講させなければならないこととされています。