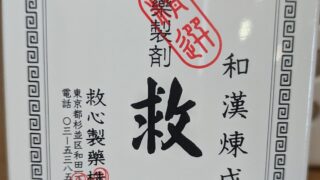令和7年度の手引きの改訂により追加された
紅麹関連製品による健康被害問題は、2024年3月に小林製薬が、同社の製造する紅麹成分を含む健康食品(機能性表示食品)を摂取した人に腎疾患などの健康被害が発生したと発表したことから表面化しました。
具体的には、腎機能障害、尿の異常(蛋白尿、血尿など)、倦怠感、食欲不振、むくみなどが見られ、重症例では急性腎不全に至り、死亡例も複数報告されています。
その後、厚生労働省は、健康被害の原因物質について、小林製薬が自主検査で検出した「プベルル酸」である可能性が高いと発表していますが、プベルル酸は、青カビが生成する天然化合物で、強い毒性を持つことが知られています。
このプベルル酸は、小林製薬の工場内(大阪工場、2023年12月閉鎖)に存在した青カビが、紅麹の培養段階で混入し、増殖する過程で産生されたと推定されています。
以上のような紅麹関連製品による健康被害を受けて、食品表示基準、食品衛生法の一部改正が行われ、機能性表示食品や特定保健用食品の健康被害の情報の収集及び提供が法制化され、特に機能性表示食品の健康被害情報の保健所等への提供については即日実施となりました。
そして、その関連部分が、早速問題作成の手引き(令和7年度)本文や欄外脚注に追加されており、追加された内容の一部は以下のとおりです。
機能性表示食品については、令和6年3月に発生した紅麹関連製品による健康被害を受けて、
① 事業者の責任において機能性関与成分によって健康維持・増進に資する特定の保健目的が期待できる旨を表示し、反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者(届出者)は、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報(医師が診断したものに限る。)を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に情報提供することを、食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする。
⇒機能性表示食品については、健康被害が疑われる情報は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することが定められています。(とりあえず疑われる情報を把握したら、因果関係がわからなくてもモタモタせずに速やかに報告することになっています)
② 製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品についてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とするなどの食品表示基準の改正が令和6年8月に行われ、同年9月より施行されている。
⇒GMPとは、「Good Manufacturing Practice」の略称で、医薬品の製造と品質管理に関する国際的な基準のことです。
(脚注より)
①の健康被害情報の収集及び医師の診断による健康被害情報の保健所等への提供については即日実施としているが、②の機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の届出に関する製造加工等におけるGMP基準の適用については令和8年9月1日までの経過措置期間が設けられている。
特定保健用食品についても、「特定保健用食品の表示許可等について」(次長通知)において許可等に係る食品の健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)に関する情報を収集し、その発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、当該情報を都道府県知事等に速やかに提供するとともに、当該情報について消費者庁長官に提供する体制が整っていることを許可等の要件とした。
⇒一方で、特定保健用食品については、医師の診断により当該食品による健康被害の疑いが診断され、さらにその発生拡大の恐れがある情報を得た場合について、都道府県知事等に速やかに情報提供するすることとされており、機能性表示食品よりも、やや情報の精査に余地がある情報提供ルールとなってます。
(脚注より)
このほか、食品衛生法施行規則についても、令和6年8月の改正により、健康被害と疑われる情報(医師が診断したものに限る。)を把握した特定保健用食品に係る許可を受けた者及び機能性表示食品の届出者に対して、都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)への情報提供が義務づけられた。
令和7年度試験では、この紅麹関連製品に関する問題が、高確率で出題されると思われますが、手引き欄外の脚注や、食品表示法・食品表示基準の条文等も含めると、追加内容のボリュームもかなり多いですので、とりあえずポイントだけは押さえておきましょう。