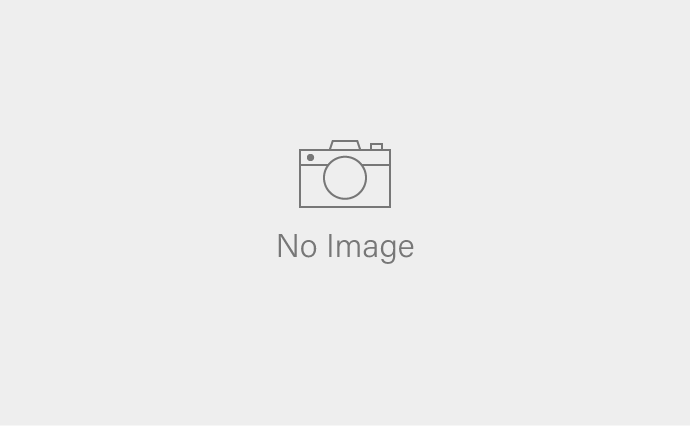いわゆるネット販売・郵送販売に関する法令。
特定販売に関しては、平成26年(2014)6月の薬事法改正で、一般用医薬品の販売が対面以外の方法で行うことができるようになったことから登場した内容です。
いわゆるECサイト(楽天、アマゾン等)による医薬品のネット通販や、漢方相談薬局における医薬品の郵送販売に関連する法令です。また、改正当時は殆ど見られませんでしたが、令和に入ったあたりから増加している、テレビCMによる医薬品の通信販売(ビタミン剤や漢方薬など)も特定販売に該当します。但し、試験対策上は、特定販売≒ネット通販と考えて差支えないでしょう。
なお、今では当たり前になっている一般用医薬品の特定販売(ネット通販)ですが、始まりはインターネットの普及が進んだ2000年代前半と言われており、旧薬事法ではネット販売自体を想定していなかったことから、当初は規制も曖昧でした。
しかしながら、平成21年(2009)6月1日、改正薬事法とそれに伴い制定された改正薬事法施行規則により、旧薬事法下で行われていた医薬品のインターネット・郵送等による通信販売が、第3類医薬品以外については全面的に禁止されることとなりました。(なお、これには漢方薬局が電話相談で販売する煎じ漢方薬(薬局製造販売医薬品)も原則含まれました)
一方で、この規制により売上を大きく減らすことになるネット通販事業者2社が、この医薬品のインターネット販売規制省令は違法だとして、国を相手に行政訴訟を起こしましたが、平成25年(2013)1月の最高裁判決により、「ネット販売を一律に禁じる厚生労働省令の規定は無効」との判断が下され、実質的にネット販売は容認せざる負えなくなりました。このような背景から、平成26年(2014)に現在の特定販売におけるルールが誕生しています。また、この際にインターネット販売できない医薬品の区分として要指導医薬品も同時に誕生しています。
登録販売者試験では、平成27年度から出題されていますが、重要ポイントのため、全国でほぼ毎年1題は出題されています。
問題作成の手引きにおける「特定販売」の定義は以下のとおり
その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」を「特定販売」という
まず、特定販売可能な医薬品の種類は必須知識です。
「一般用医薬品(1類・2類・3類)」と「薬局製造販売医薬品(毒劇薬を除く)」が可能ですが、要指導医薬品は特定販売できません。
(なお、令和5年あたりから、薬局製造販売医薬品でも、毒薬・劇薬扱いのものは特定販売できない点も出題されています)
他に良く出題されるポイントは、「ホームページに掲載する内容」についてです。
① 薬局又は店舗の主要な外観の写真
② 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
③ 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
④ 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間
⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限
①②に関して、特定販売は「薬局・店舗販売業の許可を取得した有形の店舗」しか認められていないため、写真を掲載することで実店舗を有し、医薬品も在庫していることを担保する為と考えれば良いでしょう。例えば、ホームページだけ立ち上げて販売だけ行い、在庫・配送を、店舗販売業や薬局の許可をもつ他社に外部委託するような販売方法は認められていません。
(実際には、配送センターに隣接した形式的な店舗や、雑居ビルのオフィスの一部を利用したような店舗もあります。その為、販売店舗のホームページを見ると、とても貧相な店舗写真や陳列状況の場合があります。また、ビタミン剤や漢方の通販番組でも、一瞬店舗写真や陳列状況が映ります)
③に関しては、勤務者の氏名だけで良く、「顔写真」は必要ないことを押さえて下さい。ひっかけ問題が度々登場しています。
⑤の「医薬品の使用期限」の掲載については、知らないと迷う所です。
実際、ネット通販で個々の医薬品のページを見ても記載されていませんし、結構売れている医薬品であれば、頻繁に使用期限も変わってくるので、その都度に使用期限を変更しないとダメなの?と感じる方が多いかと思います。(著者はそうでした。)
実は、これに関しては、(具体的に出題されることはありませんが)店舗概要のページ等に、「使用期限まで〇〇日以上ある医薬品をお届けします。」というような形で記載すれば良いことになっています。
とにかく、知識を定着されるためには、手引きや過去問も確認だけでなく、実際にネット販売を行っているサイトを是非確認してみて下さい。