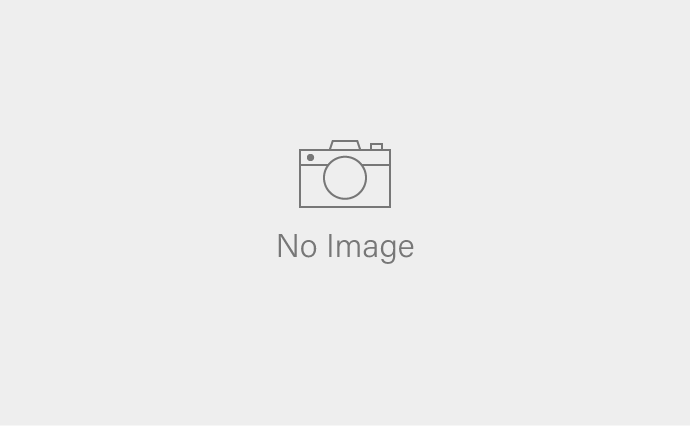簡単な問題ばかり
問11 妊婦・授乳婦の医薬品の使用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 医療用医薬品と異なり、妊婦が一般用医薬品を使用した場合における安全性に関する評価は確立されているため、一般用医薬品はすべて使用してもよい。
b 胎盤には、胎児の血液と母体の血液とが混ざらない仕組み(血液-胎盤関門)がある。
c 医薬品の種類によっては、授乳婦が使用した医薬品の成分の一部が乳汁中に移行することが知られており、母乳を介して乳児が医薬品の成分を摂取する場合がある。
d 医薬品によっては、胎児に先天異常を起こす危険性が高まるとされているものがあるが、流産や早産を誘発するおそれのあるものはない。
1(a、b) 2(b、c) 3(c、d) 4(a、d)
妊婦・授乳婦の医薬品の使用に関する問題。
a 誤り。そんな訳ない。
b 正しい。「血液-胎盤関門」についてはどうゆうものか理解しておこう。
c 正しい。
d 誤り。胎児に先天異常に関してはビタミンAの過剰摂取に関する知識は重要である。流産や早産に関しては大腸刺激性瀉下剤は注意が必要。例えばセンナ、センノシドは腸の急激な動きに刺激されて流産・ 早産を誘発するおそれがある。
正答・・・2
問12 プラセボ効果(偽薬効果)に関する記述について、誤っているものはどれか。
1 医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果という。
2 プラセボ効果によってもたらされる反応や変化には、望ましいもの(効果)と不都合なもの (副作用)とがある。
3 プラセボ効果は、主観的な変化だけでなく、客観的に測定可能な変化として現れることもあるが、不確実であり、それを目的として医薬品が使用されるべきではない。
4 プラセボ効果は、時間経過による自然発生的な変化(自然緩解など)は関与していないと考えられている。
プラセボ効果(偽薬効果)に関する問題。
医薬品を使用したとき、結果的又は偶発的に薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果(偽薬効果)という。
1 正しい。
2 正しい。検査数値の変化など、客観的に測定可能な変化として現れることもある。
3 正しい。
4 誤り。時間経過による自然発生的な変化(自然緩解など)も関与している。
正答・・・4
問13 医薬品の品質に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品を保管・陳列する場所については、清潔性が保たれるとともに、その品質が十分保持される環境となるよう留意する必要がある。
b 医薬品は、適切な保管・陳列がなされれば、経時変化による品質の劣化はない。
c 一般用医薬品では、購入された後、すぐに使用されるとは限らず、家庭における常備薬として購入されることも多いことから、使用期限から十分な余裕をもって販売等がなされることが重要である。
d 医薬品に表示されている使用期限は、未開封状態で保管された場合に品質が保持される期限である。
a b c d
1 誤 正 正 誤
2 正 正 誤 正
3 正 誤 正 誤
4 誤 正 誤 正
5 正 誤 正 正
医薬品の品質に関する問題。常識的に考えれば判断できる。
a 正しい。
b 誤り。そんなことはない。適切な保管・陳列が行われていても、経時変化による品質の劣化は避けられない。
c 正しい。
d 正しい。
正答・・・5
問14 一般用医薬品の役割に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防(科学的・合理的に効果が期待できるものに限る。)
b 軽度な疾病に伴う症状の改善
c 生活の質(QOL)の改善・向上
d 健康状態の自己検査
a b c d
1 正 正 正 誤
2 正 正 誤 正
3 正 誤 正 正
4 誤 正 正 正
5 正 正 正 正
一般用医薬品の役割に関する問題。これはaが少し迷うかもしれない。
a 正しい。
b 正しい。
c 正しい。
d 正しい。
正答・・・5
問15 一般用医薬品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品は、医薬品医療機器等法において「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」 と定義されている。
b 症状が重いときでも、医療機関の受診はせず、まずは一般用医薬品を使用することが適切な対処である。
c セルフメディケーションとは、専門家によるアドバイスを受けることなく、自己判断により一般用医薬品を利用する考え方である。
d 一般用医薬品を一定期間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化した ときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要がある。
a b c d
1 正 誤 誤 正
2 誤 正 誤 誤
3 正 誤 正 誤
4 誤 正 誤 正
5 誤 誤 正 誤
一般用医薬品に関する問題。
なお、世界保健機関(WHO)による、セルフメディケーションの定義は「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」こととされている。
a 正しい。
b 誤り。そんな訳がない。症状が重いときは受診する。
c 誤り。セルフメディケーションの主役は「一般の生活者」だが、一般用医薬品の販売に従事する専門家は、適切な情報提供を行い、セルフメディケーションを支援することが求められる。
d 正しい。
正答・・・1
問16 販売時のコミュニケーションに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
1 医薬品の販売に従事する専門家は、可能な限り、購入者側の個々の状況の把握に努めることが重要である。
2 一般用医薬品の場合、すぐに使用する必要に迫られて購入されるとは限らず、家庭における常備薬として購入されることも多いことから、その医薬品がすぐに使用される状況にあるかどうかを把握するよう努めることが望ましい。
3 購入者等が医薬品を使用する状況は随時変化する可能性があるため、販売数量は一時期に使用する必要量とする等、販売時のコミュニケーションの機会が継続的に確保されるよう配慮することが重要である。
4 購入者側に情報提供を受けようとする意識が乏しい場合には、コミュニケーションを図る必要はない。
販売時のコミュニケーションに関する問題。
常識的に判断すればよい。
1 正しい。
2 正しい。
3 正しい。
4 誤り。そうした場合でも、購入者側から医薬品の使用状況に係る情報をできる限り引き出し、コミュニケーションを図るべきである。
正答・・・4
問17 サリドマイド訴訟に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 妊娠している女性が、催眠鎮静剤等として販売されたサリドマイド製剤を使用したことにより、出生児に四肢欠損、耳の障害等の先天異常が発生したことに対する損害賠償訴訟である。
b 血管新生を妨げる作用は、サリドマイドの光学異性体のうち、一方の異性体であるS体のみが有するため、もう一方の異性体であるR体のサリドマイドを分離して製剤化すれば催奇形性は避けられる。
c この訴訟は製薬企業のみを被告として提訴され、1974年に和解が成立した。
d 日本では、1961年12月に西ドイツ(当時)の企業から勧告が届いており、かつ翌年になってからもその企業から警告が発せられていたにもかかわらず、出荷停止は1962年5月 まで行われず、販売停止及び回収措置は同年9月であるなど、対応の遅さが問題視された。
a b c d
1 正 誤 誤 正
2 誤 誤 正 誤
3 誤 正 誤 正
4 正 誤 正 誤
5 誤 正 誤 誤
サリドマイド訴訟に関する問題。
a 正しい。
b 誤り。前半部分の記述は正しいが後半が誤り。血管新生を妨げる作用は、サリドマイドの光学異性体のうち、一方の異性体(S 体)のみが有する作用であり、もう一方の異性体(R体)にはない。しかし、R体とS体は体内で相互に転換するため、R体のサリドマイドを分離して製剤化しても催奇形性は避けられない。
c 誤り。国及び製薬企業が被告として提訴された。
d 正しい。
正答・・・1
問18 第1欄の記述は、スモン訴訟に関するものである。( )の中に入れるべき字句は第2欄の どれか。
第1欄 ( )として販売されていたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症 (英名Subacute Myelo-Optico-Neuropathyの頭文字をとってスモンと呼ばれる。)に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。スモンは、その症状として初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺れや脱力、歩行困難等が現れる。麻痺は上半身にも拡がる場合があり、ときに視覚障害から失明に至ることもある。
第2欄
1 鎮咳去痰薬
2 抗アレルギー剤
3 解熱鎮痛剤
4 催眠鎮静剤
5 整腸剤
スモン訴訟に関する問題。
これは薬害関連の問題でも、かなり簡単。
正答・・・5
問19 HIV訴訟に関する記述について、正しい組み合わせはどれか。
a 血友病患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料血漿から製造された血液凝固因子製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。
b この訴訟を契機に、医薬品副作用被害救済制度が創設された。
c この訴訟を契機に、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られた。
d この訴訟の和解を踏まえ、国は、HIV感染者に対する恒久対策として、エイズ治療研究開発センター及び拠点病院の整備や治療薬の早期提供等の様々な取り組みを推進している。
a b c d
1 誤 正 正 誤
2 正 正 誤 正
3 正 誤 正 誤
4 誤 正 誤 正
5 正 誤 正 正
HIV訴訟に関する問題。
a 正しい。
b 誤り。サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、1979年に医薬品副作用被害救済制度が創設された。
c 正しい。
d 正しい。
正答・・・5
問20 CJD訴訟に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。なお、同じ記号の( )内には同じ字句が入る。
( a )外科手術等に用いられた( b )乾燥硬膜を介してクロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD)に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。CJDは、( c )の一種であるプリ オンが原因とされ、プリオンが( a )の組織に感染し、次第に認知症に類似した症状が現れ、 死に至る重篤な神経難病である。
a b c
1 脳 ヒト タンパク質
2 脳 ウシ タンパク質
3 口腔 ヒト ウイルス
4 口腔 ウシ タンパク質
5 脳 ヒト ウイルス
CJD訴訟に関する問題。
a 脳
b ヒト
c タンパク質
正答・・・1
(Visited 977 times, 1 visits today)