乗物酔い防止薬(問29)は比較的難しい
問21 かぜ及びその治療に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a かぜ薬は、原因となるウイルスの増殖を抑えたり、体内から除去することにより、かぜの諸症状の緩和を図るものである。
b 原因となるウイルスには、ライノウイルス、アデノウイルスなどがある。
c 発熱、咳、鼻水など症状がはっきりしている場合には、総合感冒薬ではなく、それぞれの症状に合わせて薬を選択することが望ましい。
d 急激な発熱を伴う場合や、症状が4日以上続くとき、又は症状が重篤なときは、かぜではない可能性が高い。
a b c d
1 正 誤 正 誤
2 正 誤 正 正
3 正 正 誤 誤
4 誤 正 正 正
5 誤 正 誤 正
問21 かぜ及びその治療に関する問題
a 誤 かぜ薬は、ウイルスの増殖を抑えたり、体内から除去するものではなく、かぜによる咳や発熱など、それら諸症状の緩和を図る対症療法薬である。
b 正
c 正
d 正
正解・・・4
問22 かぜ薬(総合感冒薬)の配合成分とその配合目的との関係について、正しいものの組合せを選べ。
配合成分 配合目的
a メチルエフェドリン塩酸塩 / 鼻粘膜の充血を和らげ、気管・気管支を拡げる。
b メキタジン / 熱を下げる。
c ブロムヘキシン塩酸塩 / 痰の切れを良くする。
d ノスカピン / 炎症による腫れを和らげる。
1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
かぜ薬(総合感冒薬)の配合成分とその配合目的との関係に関する問題
a 正 メチルエフェドリン塩酸塩はアドレナリン作動成分である。
b 誤 メキタジンは抗ヒスタミン成分である。
c 正 ブロムヘキシン塩酸塩は去痰成分である。
d 誤 ノスカピンは非麻薬性鎮咳成分である。
正解・・・2
問23 かぜ薬(総合感冒薬)の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 解熱鎮痛成分として、サリチルアミド、イソプロピルアンチピリン等が用いられる。
b エテンザミドは、15歳未満の小児で水痘にかかっているときは使用を避ける。
c アドレナリン作動成分として、クレマスチンフマル酸塩が用いられる。
d 抗コリン成分として、グリチルリチン酸二カリウムが用いられる。
a b c d
1 正 正 誤 誤
2 誤 正 正 誤
3 誤 誤 正 正
4 誤 誤 誤 正
5 正 誤 誤 誤
かぜ薬(総合感冒薬)の配合成分に関する問題
a 正
↓サリチルアミドを含有した総合感冒薬
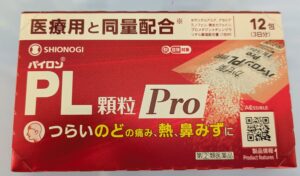
b 正 これはライ症候群の発生に関する記述であることを理解しておくこと。
なお、ライ症候群とは、主として小児が水痘 (水疱瘡)やインフルエンザ等のウイルス性疾患に罹っているときに、激しい嘔吐や意識障害、痙攣等の急性脳症の症状を呈する症候群で、その発生はまれであるが死亡率が高く、生存の場合も予後は不良である。
サリチル酸系解熱鎮痛成分は、このライ症候群の発生と関連が示唆されているため、小児での使用が制限されている。(なお、エテンザミドよりも、アスピリン・サザピリンはより厳しく、15歳未満の小児は、いかなる場合も一般用医薬品としては使用できない。)
c 誤 クレマスチンフマル酸塩は抗ヒスタミン成分である。
d 誤 グリチルリチン酸二カリウムは抗炎症成分である。
正解・・・1
問24 かぜの症状緩和に用いられる漢方処方製剤のうち、体力虚弱な人に用いるものの組合せを選べ。
a 葛根湯
b 桂枝湯
c 小柴胡湯
d 香蘇散
1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
どれも風邪症状に用いられる漢方薬だが、しばり表現における「体力」の記述は以下のとおりである。
a 誤 葛根湯:体力中等度以上
b 正 桂枝湯:体力虚弱
c 誤 小柴胡湯:体力中等度
d 正 香蘇散:体力虚弱
正解・・・4
問25 解熱鎮痛薬(生薬成分を除く。)及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 発熱や痛みの原因となっている病気や外傷を根本的に治すことを目的とする。
b 飲酒によって、解熱鎮痛薬による胃腸障害が増強する可能性がある。
c アスピリンには血液を凝固しにくくさせる作用がある。
d アスピリン喘息は、アスピリン特有の副作用ではなく、他の解熱鎮痛成分でも生じる可能性がある。
a b c d
1 正 誤 正 誤
2 正 誤 誤 正
3 誤 正 正 正
4 誤 正 誤 正
5 誤 誤 正 正
解熱鎮痛薬(生薬成分を除く。)及びその配合成分に関する問題
a 誤 解熱鎮痛薬の使用は、発熱や痛みを一時的に抑える対症療法であって、疾病の原因を根本的に解消するものではない。
b 正
c 正 なお、医療用医薬品のアスピリンは、血栓ができやすい人に対する血栓予防薬の成分としても用いられている。
↓医療用として使用されているアスピリン製剤

d 正 アスピリン喘息は、アスピリン特有の副作用ではなく、他の解熱鎮痛成分でも生じる可能性がある。
正解・・・3
問26 鎮痛の目的で用いられる漢方処方製剤に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 呉茱萸湯は、体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの頭痛、頭痛に伴う吐きけ・嘔吐、しゃっくりに適すとされる。
b 釣藤散は、体力に関わらず使用でき、筋肉の急激な痙攣を伴う痛みのあるもののこむらがえり、筋肉の痙攣、腹痛、腰痛に適すとされる。
c 桂枝加朮附湯は、体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの関節痛、神経痛に適すとされる。
d 芍薬甘草湯は、体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるものに適すとされる。
a b c d
1 正 誤 正 誤
2 誤 正 正 誤
3 誤 誤 正 正
4 正 正 誤 誤
5 正 誤 誤 正
鎮痛の目的で用いられる漢方処方製剤に関する問題
a 正 呉茱萸湯は「頭痛に伴う吐きけ」のほか、「しゃっくり」が特徴的なキーワードである。
b 誤 釣藤散ではなく芍薬甘草湯に関する記述である。芍薬甘草湯は「こむらがえり」「筋肉の痙攣」に用いられる漢方として非常に有名。
c 正 これは桂枝加朮附湯に関する記述で、「手足が冷えてこわばり」が特徴的なキーワードである。例えば、閉経以降の女性にみられる手指の関節の痛みに用いられるイメージを持つと良いでしょう。「体力虚弱」も結びつけやすくなります。
d 誤 芍薬甘草湯ではなく釣藤散に関する記述である。釣藤散は「慢性頭痛」が特徴的なキーワードである。
正解・・・1
問27 一般用医薬品の解熱鎮痛薬購入者に対する登録販売者の説明について、適切なものの組合せを選べ。
a 発熱が1週間以上続く場合は、服用量を増やしてください。
b 年月の経過に伴って月経痛が悪化している場合は、病院を受診してください。
c 頭痛に対して使用する場合には、症状が出る前に服用してください。
d 肝機能障害を起こすことがあるので、服用期間中の飲酒はやめてください。
1(a、b) 2(a、c) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
一般用医薬品の解熱鎮痛薬購入者に対する登録販売者の説明に関する問題
関西広域ブロックではこのような販売現場を想定した問題が時折出題されます。
a 誤 常識的におかしいとわかるでしょう。、発熱が1週間以上続いているような場合は、単なるかぜが原因ではなく、かぜ以外の感染症やその他の重大な病気が原因となっている可能性があるため、受診勧奨を行うべきである。
b 正
c 誤 解熱鎮痛薬は、頭痛の症状が軽いうちに服用すると効果的であるが、症状が現れないうちに予防的に使用することは適切でない。
d 正
正解・・・4
問28 眠気防止薬及びその配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 小児用の眠気防止薬はない。
b かぜ薬を使用したことによる眠気を抑えるために、眠気防止薬を使用することは適切ではない。
c カフェインには、腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収抑制作用がある。
d 眠気防止薬におけるカフェインの1回摂取量はカフェインとして20mg、1日摂取量はカフェインとして50mgが上限とされている。
a b c d
1 正 誤 正 正
2 正 正 正 誤
3 正 正 誤 誤
4 誤 正 誤 正
5 誤 誤 正 正
眠気防止薬及び、その有効成分として配合されるカフェインに関する問題。
a 正
b 正
c 正
d 誤 眠気防止薬におけるカフェインの1回摂取量はカフェインとして200mg、1日摂取量はカフェインとして500mgが上限とされている。
↓カフェインを配合した眠気防止薬

正解・・・2
問29 乗物酔い防止薬の配合成分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a ジフェニドール塩酸塩は、前庭神経の調節作用と内耳への血流改善作用を示す。
b メクリジン塩酸塩は、他の抗ヒスタミン成分と比べて作用の持続時間が短い。
c スコポラミン臭化水素酸塩水和物は、中枢に作用して自律神経系の混乱を軽減させるとともに、末梢では消化管緊張低下作用を示す。
d ジプロフィリンは、脳の興奮を抑制するキサンチン系成分である。
a b c d
1 誤 正 正 誤
2 正 正 誤 正
3 正 誤 正 誤
4 誤 正 誤 正
5 正 誤 正 正
乗物酔い防止薬の配合成分に関する問題
前年と同じ4成分から出題だが、その作用を細かく問われており難易度は高め。
a 正 ジフェニドール塩酸塩は抗めまい成分で、内耳にある前庭と脳を結ぶ神経(前庭神経)の調節作用のほか、内耳への血流を改善する作用を示す。
b 誤 メクリジン塩酸塩は乗り物酔い防止薬として使用される抗ヒスタミン成分で、他の抗ヒスタミン成分と比べて作用が現れるのが遅く持続時間が長い。
c 正 なお、スコポラミン臭化水素酸塩水和物は乗り物酔い防止薬として使用される抗コリン成分で、肝臓で速やかに代謝されてしまうため、抗ヒスタミン成分等と比べて作用の持続時間は短い。(持続時間の違いはメクリジンとセットで学習を)
d 正
↓スコポラミン臭化水素酸塩水和物、メクリジン塩酸塩が配合された乗物酔い防止薬

正解・・・3
問30 次の記述にあてはまる漢方処方製剤として、最も適切なものを選べ。
体力虚弱で疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿及び多尿などを伴うものの小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜なきに適すとされる。
1 柴胡加竜骨牡蛎湯
2 桂枝加芍薬湯
3 小建中湯
4 抑肝散
5 白虎加人参湯
「小児虚弱体質」「小児夜尿症」というキーワードから容易に小建中湯を選べるように。
正解・・・3

