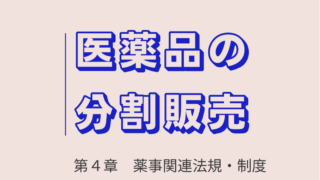偽アルドステロン症は、アルドステロンというホルモンの働きが過剰になっているかのように見える病態
偽アルドステロン症は、試験では超頻出ポイントですが、しっかり理解しようとするとかなり大変です。
とりあえず、試験対策の最小限の知識として、問題作成の手引きに記載された、その定義、主な症状、偽アルドステロン症を起こしやすい成分は以下の通りです。
「体内に塩分(ナトリウム)と水が貯留し、体からカリウムが失われることによって生じる病態である。副腎皮質からのアルドステロン分泌が増加していないにもかかわらずこのような状態となることから、偽アルドステロン症と呼ばれている。」
「主な症状に、手足の脱力、血圧上昇、筋肉痛、こむら返り、倦怠感、手足のしびれ、頭痛、むくみ(浮腫)、 喉の渇き、吐きけ・嘔吐等があり、病態が進行すると、筋力低下、起立不能、歩行困難、痙攣等を生じる。」
「偽アルドステロン症を生じる恐れがある主な成分に、「カンゾウ(甘草)、グリチルリチン酸、グリチルリチン酸二カリウム、グリチルレチン酸」がある。」
以上、赤字の部分は試験対策上、最低限押さえておいて下さい。
とりあえずは、体に水分・ナトリウムが過剰に貯留され、逆にカリウムは必要以上に失うことによって発症し、原因となる成分として、カンゾウ(甘草)、グリチルリチン酸等の過剰摂取があるんだなぁと、まずは押さえておいてください。
なお、症状については全て覚えるのは大変なので、「体内に塩分と水が貯留」することと結びつけやすい「血圧上昇」「むくみ(浮腫)」をまずは覚えると良いでしょう。また、体内のNa、Kは、筋肉の収縮や神経の伝達に関与していることも知っていると、他の症状も結びつけやすいはずです。
↓カンゾウ(甘草)の片(スライスしたもの)。補気剤として薬膳料理にも利用されます。

試験対策としては、以上である程度対応できますが、もう少し「アルドステロン」「アルドステロン症」についても触れておきます。
まずは、アルドステロンと言うホルモンですが・・・
「アルドステロンとは副腎皮質で分泌されるステロイドホルモンの1種で、腎臓における尿細管に作用しナトリウム・水分の再吸収、カリウム再吸収の抑制に働き、血圧・体液の調節に関連するホルモンである。」
⇒なお、ここでNa(及び水分)とKが対の関係になっていますが、「Na-Kポンプ(ナトリウム-カリウムポンプ)」について、少しでも知っていると理解しやすいです。
このNa-Kポンプは、ヒトの細胞膜にあるタンパク質で、細胞内外のナトリウムイオン(Na+)とカリウムイオン(K+)の濃度勾配を調節して、神経細胞や筋細胞の興奮に関係したり、体内の水分量の調節に関与しています。
そして、腎臓の尿細管におけるNa-Kポンプはアルドステロンの働きによって活性化され、結果的に体内にNa・水分が再吸収され、逆にカリウムは再吸収が抑制されますが、アルドステロンが必要以上に放出されると、体液量の増加による浮腫みや血圧上昇、筋肉の脱力や痙攣等、低カリウム血症につながります(アルドステロン症)。
(Na-Kポンプは、ナトリウムイオン(Na+)を細胞内から細胞外へ汲み出し、逆にカリウムイオン(K+)を細胞外から細胞内へ汲み入れるますが、尿細管では主に(尿が流れる側ではなく)血管側に存在し、そこでの働きを説明すると、話が複雑になるので割愛)
「偽アルドステロン症とは、カンゾウ等を含む薬剤の影響などにより、アルドステロンというホルモンが必要以上に分泌されたような状態になること(つまり、ナトリウム・水分の再吸収、カリウム再吸収抑制が過剰に起こる)である。」
⇒実際にはアルドステロンの分泌は増えていないにも関わらず、増えたときと同じような病態を示すことから「偽」が付けられていると理解すると良いでしょう。
ここで、グリチルリチン酸等が、どのような作用で偽アルドステロン症になるかまで理解しようとすると、かなり大変です。
これに関して詳細まで理解する必要はありませんが、グリチルリチン酸等が、アルドステロンと同様な働きをする訳ではなく、グリチルリチン酸が体内で代謝されて生じたグリチルレチン酸が、アルドステロンと似た性質のホルモンの1種であるコルチゾールを、コルチゾンに変換する酵素の活性を阻害することで、生じることがわかっています。
これにより、コルチゾールが(Na・水分の再吸収に影響しない)コルチゾンに変換されにくくなり、腎臓の細胞内でコルチゾールの濃度が異常に高まります。この高濃度のコルチゾールが、腎臓の尿細管で、アルドステロンと同じような作用を発揮してしまうことで、偽アルドステロン症を生じてしまうことがわかっています。
なお、偽アルドステロン症については、厚生労働省より「重篤副作用疾患別対応マニュアル 」(←第2章で出題されることあり)が公開されているので、興味のある方は是非、確認してみて下さい。
注意したい漢方薬(芍薬甘草湯)
この「偽アルドステロン症」は昭和50年代に、抗炎症作用もあるグリチルリチン酸を配合した医薬品による副作用で特に注目されましたが、現在市販薬でそれ程問題にはなっていないものの、今でも注意は必要です。
そして、市販薬の中でも特に注意したいのは、足の攣り(こむら返り)に良く用いられる「芍薬甘草湯」です。カンゾウ(甘草)を含む漢方薬は数多くありますが、特に「芍薬甘草湯」には、多く含まれています。
この芍薬甘草湯は、攣った直後や、予兆時に服用すると症状がすぐに和らぐという方も多く、人気・効果の高い漢方薬の一つです。
その為、ドラックストア等での市販はもちろん、医療機関でも良く処方されています。
(正確な統計データは分かりませんが、100種類以上存在する医療用エキス製剤の中では、処方頻度(処方金額、処方量は別)は一番多いかもしれません。「68番の漢方」として有名です。)
しかし、その効果感の良さから、漫然と1日何度も服用し、いつの間にか浮腫んで体重が増えてきたり、血圧が上昇してきたという話は聞いたことがあります。
一般用医薬品販売の現場でも、「芍薬甘草湯」は人気製品の一つですが、他に複数の漢方薬を飲んでいる可能性のある方や、頻繁に購入しているケースがあれば、一応注意を払うべきでしょう。
参考資料:厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル 「偽アルドステロン症」(令和4年2月改訂)
https://www.pmda.go.jp/files/000245267.pdf