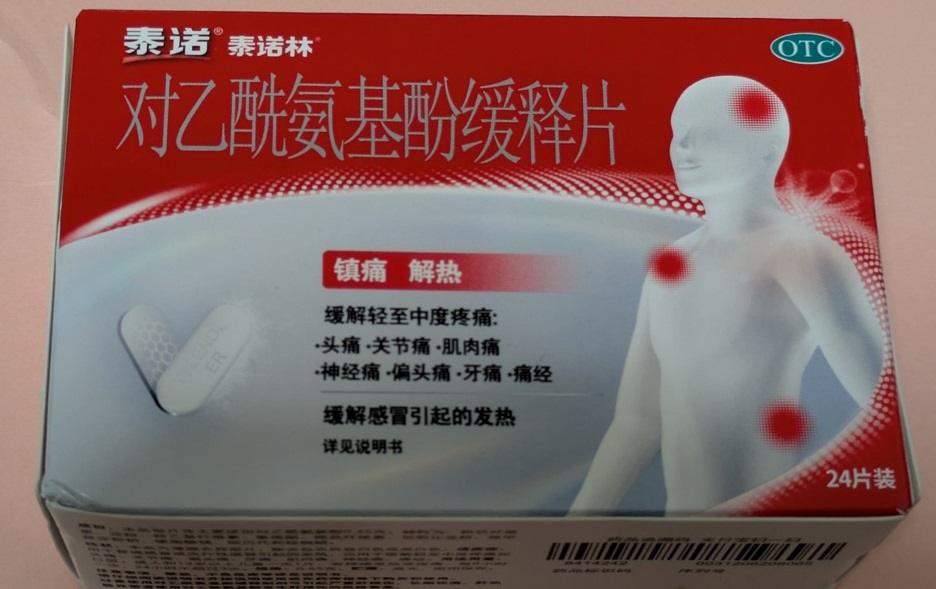涼茶(リョンチャー)は、香港をはじめとする広東省などで古くから飲まれている、複数の薬草(生薬)を煮だしてつくった伝統的な飲み物で、「漢方茶」といった方がイメージしやすいかもしれません。
また、「涼」という字が入っていますが、必ずしも冷たいお茶という訳ではなく、体内の熱や湿気を取り除く効果があるような効能が期待できることから「涼茶」と名付けられたようです。
なお、一般に清熱作用のある漢方薬は黄連解毒湯や温清飲のように、苦みの強いものが多いですが、涼茶についても、苦みの強いものが多いです。(甘い涼茶もあります)


この涼茶の起源ですが、高温多湿な広東地域の気候風土と深く結びついており、この地域では、古くから湿気や暑さによる体調不良が多かったため、人々は経験的に、体内のバランスを整える効果のある薬草を煎じて飲む習慣を持っていました。そのような習慣が発展し、涼茶を飲む文化に繋がったと言われています。
そして、広東地域ではこのような涼茶を専門に販売するお店「涼茶舗(リョンチャーポー)」が、近代以降に数多く登場しました。これらの店では、様々な種類の涼茶が提供され、人々の日常に深く根付き、現在でも受け継がれています。
(なお、涼茶舗では、亀苓膏(亀ゼリー)を提供しているお店も多く、両方喫食することもできます。)
涼茶の種類について
涼茶にも、様々な種類があり、その時の体調や症状に合わせて選ぶことができますが、その中でも代表的なのは、「廿四味(ヤーセイメイ)」、「五花茶(ンーファチャー)」です。

「廿四味(ヤーセイメイ)」
涼茶の中でも特に代表的なものの一つで、高温多湿な気候の広東地域において、「湿邪を取り除く」「暑さを和らげる」ための涼茶と言われており、24種類の薬草を使用していることから名付けられてます。
但し、涼茶舗によってそれぞれ独自のレシピがあり、実際の薬草の種類は店ごとに様々です。
使用されている薬草としては、
蒲公英(タンポポ)、金銀花、桑の葉、魚腥草(ドクダミ)、玉竹、百合、桔梗・・・等が使用されています。

「五花茶(ンーファチャー)」
「五花」という名前の通り、一般に5種類の花を煮だして作られますが、こちらも地域や涼茶舗によって配合される花の種類は多少異なるそうです。良く使用される5種類の組合せと期待される効果は・・・
・金銀花(きんぎんか): スイカズラの花の蕾を乾燥させたもの。解熱、解毒、抗炎症作用があるとされる。
・菊花(きっか): キクの花を乾燥させたもの。解熱、鎮静、目の疲れを和らげる効果があるとされる。
・雞蛋花(けいらんか、ジーダンファー): プルメリアの花。清熱、解暑、利湿の効果があるとされる。
・木棉花(もめんか、ムーミエンファー): パンヤノキの花。清熱、利湿、解毒の効果があるとされる。
・槐花(かいか、ホワイファー): エンジュの花の蕾を乾燥させたもの。清熱、涼血、止血の効果があるとされる。
となっており、こちらも主に熱邪や湿邪向けの薬草で構成されています。

他にも「感冒茶(風邪茶)」や「桔梗茶(止咳茶)」など、様々な涼茶があり、その時の体調等によって自分にあったものを選ぶことができます。また、飲みやすくするために甘みを加えた製品や、ペットボトルや缶入りの涼茶も販売されています。
なお、香港や広州などの中国の広東地域で現在も根付いた文化である「涼茶」ですが、2006年に、中国本土の「涼茶」が国家級非物質文化遺産に登録されました。これは、涼茶が単なる飲み物ではなく、中国の伝統文化の一つとして重要な役割を果たしていることを示していると言えるでしょう。
このように、涼茶は地域の気候風土の中で生まれた生活の知恵であり、人々の健康を支えてきた、広東地域の食文化ですが、地元民はもちろん、外国人観光客でも手軽に立ち寄ることができるので、高温多湿な香港で少し疲れを感じた時など、涼茶を体験してみるのも良いかもしれません。